・粒子性は実は遠隔作用性(光は波でも粒子でもない)
本来、遠隔作用である電磁気作用が、周囲に存在する物質の疑似エーテル的な働きによ
り、近接作用的に伝わってしまうことは、すでに述べた。だが、あらゆる場合において、
電磁気作用が疑似近接作用的になるわけではない。
たとえば、下図のような問題の場合、物体Aと物体Bとの間の距離がある程度大きい場
合は、この二つの物体間に働く電磁気作用は、(疑似)近接作用的になる。
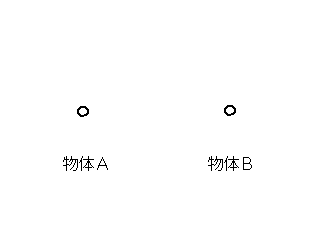 ところが、距離が小さくなってくると、物体間に働く電磁気作用は、遠隔作用的になって
くる。この理由は、電磁気作用の大きさが距離と関係あるからである。電磁気作用は、距
離が近くなるほど大きい。このため、作用を及ぼし合う二物体間の距離が近くなるほど、
相対的に、それ以外の物質(すなわち疑似エーテル)の干渉の度合いが小さくなる。この
ため、疑似エーテルの働きが弱まり、(疑似)近接作用性が弱まって、本来の遠隔作用性
が強まってくるのである。つまり、疑似エーテルから受ける作用よりも、二物体間に直接
的に働く作用が、相対的に大きくなるために、遠隔作用的になるのである。
このように、物体間の距離が小さくなると、物体間に働く作用は、遠隔作用的になるの
である。一方、すでに述べたように、遠隔作用では、作用を及ぼし合う物体は、完全弾性
衝突を起こしているかのように振る舞う。このとこから、物質を構成している素粒子の荷
電粒子について、次のようなことが予想される。
荷電粒子は運動(振動)しているので、電場が誘導され、他の荷電粒子と互いに作用を
及ぼしあう。しかも、荷電粒子間の距離は非常に小さいので、その作用は遠隔作用的なも
のになる。したがって、荷電粒子どうしは完全弾性衝突をしているかのように振る舞うこ
とになる。ということは、物質を構成している荷電粒子は、マックスウェルの気体分子の
分布式にしたがうように振る舞うはずである。なぜなら、マックスウェルの分布式は、気
体分子が完全弾性衝突することを前提に作られたものだからである。
興味深いことに、すでにこのことを示す公式が提唱されている。それが、黒体輻射に関
する『ウィーンの公式』である。アインシュタインは、ウィーンの公式を『光の粒子性を
示すもの』と解釈したが、実は、電磁気作用の遠隔作用性を示すものだったのである。さ
らに、このことから、従来、光の粒子を示すといわれてきた現象(光電効果やコンプトン
散乱など)が、実は、電磁気作用の遠隔作用性を示すものだったこともわかるだろう。実
際、光電効果も、コンプトン効果も、あたかも完全弾性衝突のように、電子がはじき出さ
れる現象である。
ところが、距離が小さくなってくると、物体間に働く電磁気作用は、遠隔作用的になって
くる。この理由は、電磁気作用の大きさが距離と関係あるからである。電磁気作用は、距
離が近くなるほど大きい。このため、作用を及ぼし合う二物体間の距離が近くなるほど、
相対的に、それ以外の物質(すなわち疑似エーテル)の干渉の度合いが小さくなる。この
ため、疑似エーテルの働きが弱まり、(疑似)近接作用性が弱まって、本来の遠隔作用性
が強まってくるのである。つまり、疑似エーテルから受ける作用よりも、二物体間に直接
的に働く作用が、相対的に大きくなるために、遠隔作用的になるのである。
このように、物体間の距離が小さくなると、物体間に働く作用は、遠隔作用的になるの
である。一方、すでに述べたように、遠隔作用では、作用を及ぼし合う物体は、完全弾性
衝突を起こしているかのように振る舞う。このとこから、物質を構成している素粒子の荷
電粒子について、次のようなことが予想される。
荷電粒子は運動(振動)しているので、電場が誘導され、他の荷電粒子と互いに作用を
及ぼしあう。しかも、荷電粒子間の距離は非常に小さいので、その作用は遠隔作用的なも
のになる。したがって、荷電粒子どうしは完全弾性衝突をしているかのように振る舞うこ
とになる。ということは、物質を構成している荷電粒子は、マックスウェルの気体分子の
分布式にしたがうように振る舞うはずである。なぜなら、マックスウェルの分布式は、気
体分子が完全弾性衝突することを前提に作られたものだからである。
興味深いことに、すでにこのことを示す公式が提唱されている。それが、黒体輻射に関
する『ウィーンの公式』である。アインシュタインは、ウィーンの公式を『光の粒子性を
示すもの』と解釈したが、実は、電磁気作用の遠隔作用性を示すものだったのである。さ
らに、このことから、従来、光の粒子を示すといわれてきた現象(光電効果やコンプトン
散乱など)が、実は、電磁気作用の遠隔作用性を示すものだったこともわかるだろう。実
際、光電効果も、コンプトン効果も、あたかも完全弾性衝突のように、電子がはじき出さ
れる現象である。
次ページへ
目次へ

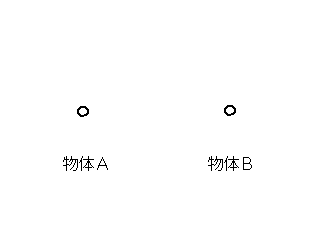 ところが、距離が小さくなってくると、物体間に働く電磁気作用は、遠隔作用的になって
くる。この理由は、電磁気作用の大きさが距離と関係あるからである。電磁気作用は、距
離が近くなるほど大きい。このため、作用を及ぼし合う二物体間の距離が近くなるほど、
相対的に、それ以外の物質(すなわち疑似エーテル)の干渉の度合いが小さくなる。この
ため、疑似エーテルの働きが弱まり、(疑似)近接作用性が弱まって、本来の遠隔作用性
が強まってくるのである。つまり、疑似エーテルから受ける作用よりも、二物体間に直接
的に働く作用が、相対的に大きくなるために、遠隔作用的になるのである。
このように、物体間の距離が小さくなると、物体間に働く作用は、遠隔作用的になるの
である。一方、すでに述べたように、遠隔作用では、作用を及ぼし合う物体は、完全弾性
衝突を起こしているかのように振る舞う。このとこから、物質を構成している素粒子の荷
電粒子について、次のようなことが予想される。
荷電粒子は運動(振動)しているので、電場が誘導され、他の荷電粒子と互いに作用を
及ぼしあう。しかも、荷電粒子間の距離は非常に小さいので、その作用は遠隔作用的なも
のになる。したがって、荷電粒子どうしは完全弾性衝突をしているかのように振る舞うこ
とになる。ということは、物質を構成している荷電粒子は、マックスウェルの気体分子の
分布式にしたがうように振る舞うはずである。なぜなら、マックスウェルの分布式は、気
体分子が完全弾性衝突することを前提に作られたものだからである。
興味深いことに、すでにこのことを示す公式が提唱されている。それが、黒体輻射に関
する『ウィーンの公式』である。アインシュタインは、ウィーンの公式を『光の粒子性を
示すもの』と解釈したが、実は、電磁気作用の遠隔作用性を示すものだったのである。さ
らに、このことから、従来、光の粒子を示すといわれてきた現象(光電効果やコンプトン
散乱など)が、実は、電磁気作用の遠隔作用性を示すものだったこともわかるだろう。実
際、光電効果も、コンプトン効果も、あたかも完全弾性衝突のように、電子がはじき出さ
れる現象である。
ところが、距離が小さくなってくると、物体間に働く電磁気作用は、遠隔作用的になって
くる。この理由は、電磁気作用の大きさが距離と関係あるからである。電磁気作用は、距
離が近くなるほど大きい。このため、作用を及ぼし合う二物体間の距離が近くなるほど、
相対的に、それ以外の物質(すなわち疑似エーテル)の干渉の度合いが小さくなる。この
ため、疑似エーテルの働きが弱まり、(疑似)近接作用性が弱まって、本来の遠隔作用性
が強まってくるのである。つまり、疑似エーテルから受ける作用よりも、二物体間に直接
的に働く作用が、相対的に大きくなるために、遠隔作用的になるのである。
このように、物体間の距離が小さくなると、物体間に働く作用は、遠隔作用的になるの
である。一方、すでに述べたように、遠隔作用では、作用を及ぼし合う物体は、完全弾性
衝突を起こしているかのように振る舞う。このとこから、物質を構成している素粒子の荷
電粒子について、次のようなことが予想される。
荷電粒子は運動(振動)しているので、電場が誘導され、他の荷電粒子と互いに作用を
及ぼしあう。しかも、荷電粒子間の距離は非常に小さいので、その作用は遠隔作用的なも
のになる。したがって、荷電粒子どうしは完全弾性衝突をしているかのように振る舞うこ
とになる。ということは、物質を構成している荷電粒子は、マックスウェルの気体分子の
分布式にしたがうように振る舞うはずである。なぜなら、マックスウェルの分布式は、気
体分子が完全弾性衝突することを前提に作られたものだからである。
興味深いことに、すでにこのことを示す公式が提唱されている。それが、黒体輻射に関
する『ウィーンの公式』である。アインシュタインは、ウィーンの公式を『光の粒子性を
示すもの』と解釈したが、実は、電磁気作用の遠隔作用性を示すものだったのである。さ
らに、このことから、従来、光の粒子を示すといわれてきた現象(光電効果やコンプトン
散乱など)が、実は、電磁気作用の遠隔作用性を示すものだったこともわかるだろう。実
際、光電効果も、コンプトン効果も、あたかも完全弾性衝突のように、電子がはじき出さ
れる現象である。