・遠隔作用と疑似近接作用の混合
荷電粒子間の作用が遠隔作用的になるには、荷電粒子間の距離に加えて、振動数すなわ
ち波長が関係してくる。わかりやすい例として、下図のような問題を考えよう。
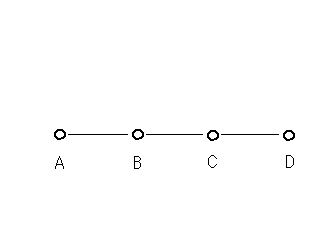 振動数が低いときは波長も長いので、これらの荷電粒子は(疑似)近接作用的に振る舞う。
ところが、振動数が高いと波長が短くなる。そして、波長が荷電粒子間の距離の二倍未満
になってしまうと、もはや荷電粒子は(疑似)近接作用的に振る舞うことができなくなる。
このため、荷電粒子は遠隔作用的に振る舞うようになるのである。
これは、情報処理における『シャノンの標本化定理』と似ている。CDやMDのような
デジタル・オーディオでは、アナログ信号をデジタル信号に変換して記録されるわけだが、
標本化周波数の1/2を超える周波数の信号は、正しく変換できない。
これと同じように、上記の問題でも、周波数がある値よりも高いとき、すなわち、波長
がある値よりも短いとき、荷電粒子は(疑似)近接作用的に振る舞うことができず、遠隔
作用的に振る舞うことになるのである。
ちなみに、荷電粒子が(疑似)近接作用的に振る舞っている時は、作用によって受け取
った運動量や運動エネルギーが、各荷電粒子に分散される。ところが、遠隔作用的に振る
舞うときは分散されないので、作用を受けた粒子に運動量や運動エネルギーが集中するこ
とになる。このため、その荷電粒子だけが特別に大きな作用を受け、(場合によっては)
物質中からはじき出されることになる。これが、光電効果であり、コンプトン散乱なので
ある。これらは、共に波長の短い(周波数の高い)時に起こる現象である。
このように、波長の短い(周波数の高い)時は、遠隔作用性が強まるのである。すでに
取り上げたウィーンの公式も、波長の短い(周波数の高い)時に非常によい近似を示すも
のである。光の粒子性とは、実は、電磁気作用の遠隔作用性だったのである。
これに対し、波長の長い(周波数の低い)時は、(疑似)近接作用性が強まる。このた
め、荷電粒子は波動的に振る舞う。したがって、黒体輻射の問題では『レイリー・ジーン
ズの公式』が成り立つことになるのである。つまり、レイリー・ジーンズの公式は、光の
波動性を示すというよりは、電磁気作用の疑似近接作用性を示すものだったのである。
以上のことをまとめていうならば、物質の世界では、遠隔作用と疑似近接作用とが混在
しているということである。波長が短く(周波数が高く)なれば遠隔作用性が強まり、波
長が長く(周波数が低く)なれば疑似近接作用性が強まる。プランクの公式も、実は、こ
のことを示しているのである。
ちなみに、プランクは、ウィーンの公式とレイリー・ジーンズの公式とを算術的に折衷
して、自身の公式を導いた。そして、その理論的根拠を後から考え出した。それが、『エ
ネルギー量子化仮説』であった。そして、その考えをさらに押し進めたのが、アインシュ
タインの『光量子仮説』であった。
だが、すでに見てきたように、そのような荒唐無稽な考え方は、もはや不要である。光
は波でも粒子でもないのだ。
振動数が低いときは波長も長いので、これらの荷電粒子は(疑似)近接作用的に振る舞う。
ところが、振動数が高いと波長が短くなる。そして、波長が荷電粒子間の距離の二倍未満
になってしまうと、もはや荷電粒子は(疑似)近接作用的に振る舞うことができなくなる。
このため、荷電粒子は遠隔作用的に振る舞うようになるのである。
これは、情報処理における『シャノンの標本化定理』と似ている。CDやMDのような
デジタル・オーディオでは、アナログ信号をデジタル信号に変換して記録されるわけだが、
標本化周波数の1/2を超える周波数の信号は、正しく変換できない。
これと同じように、上記の問題でも、周波数がある値よりも高いとき、すなわち、波長
がある値よりも短いとき、荷電粒子は(疑似)近接作用的に振る舞うことができず、遠隔
作用的に振る舞うことになるのである。
ちなみに、荷電粒子が(疑似)近接作用的に振る舞っている時は、作用によって受け取
った運動量や運動エネルギーが、各荷電粒子に分散される。ところが、遠隔作用的に振る
舞うときは分散されないので、作用を受けた粒子に運動量や運動エネルギーが集中するこ
とになる。このため、その荷電粒子だけが特別に大きな作用を受け、(場合によっては)
物質中からはじき出されることになる。これが、光電効果であり、コンプトン散乱なので
ある。これらは、共に波長の短い(周波数の高い)時に起こる現象である。
このように、波長の短い(周波数の高い)時は、遠隔作用性が強まるのである。すでに
取り上げたウィーンの公式も、波長の短い(周波数の高い)時に非常によい近似を示すも
のである。光の粒子性とは、実は、電磁気作用の遠隔作用性だったのである。
これに対し、波長の長い(周波数の低い)時は、(疑似)近接作用性が強まる。このた
め、荷電粒子は波動的に振る舞う。したがって、黒体輻射の問題では『レイリー・ジーン
ズの公式』が成り立つことになるのである。つまり、レイリー・ジーンズの公式は、光の
波動性を示すというよりは、電磁気作用の疑似近接作用性を示すものだったのである。
以上のことをまとめていうならば、物質の世界では、遠隔作用と疑似近接作用とが混在
しているということである。波長が短く(周波数が高く)なれば遠隔作用性が強まり、波
長が長く(周波数が低く)なれば疑似近接作用性が強まる。プランクの公式も、実は、こ
のことを示しているのである。
ちなみに、プランクは、ウィーンの公式とレイリー・ジーンズの公式とを算術的に折衷
して、自身の公式を導いた。そして、その理論的根拠を後から考え出した。それが、『エ
ネルギー量子化仮説』であった。そして、その考えをさらに押し進めたのが、アインシュ
タインの『光量子仮説』であった。
だが、すでに見てきたように、そのような荒唐無稽な考え方は、もはや不要である。光
は波でも粒子でもないのだ。
次ページへ
目次へ

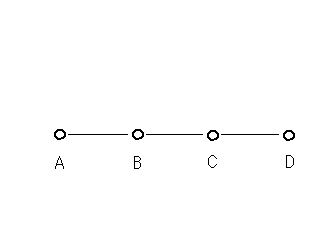 振動数が低いときは波長も長いので、これらの荷電粒子は(疑似)近接作用的に振る舞う。
ところが、振動数が高いと波長が短くなる。そして、波長が荷電粒子間の距離の二倍未満
になってしまうと、もはや荷電粒子は(疑似)近接作用的に振る舞うことができなくなる。
このため、荷電粒子は遠隔作用的に振る舞うようになるのである。
これは、情報処理における『シャノンの標本化定理』と似ている。CDやMDのような
デジタル・オーディオでは、アナログ信号をデジタル信号に変換して記録されるわけだが、
標本化周波数の1/2を超える周波数の信号は、正しく変換できない。
これと同じように、上記の問題でも、周波数がある値よりも高いとき、すなわち、波長
がある値よりも短いとき、荷電粒子は(疑似)近接作用的に振る舞うことができず、遠隔
作用的に振る舞うことになるのである。
ちなみに、荷電粒子が(疑似)近接作用的に振る舞っている時は、作用によって受け取
った運動量や運動エネルギーが、各荷電粒子に分散される。ところが、遠隔作用的に振る
舞うときは分散されないので、作用を受けた粒子に運動量や運動エネルギーが集中するこ
とになる。このため、その荷電粒子だけが特別に大きな作用を受け、(場合によっては)
物質中からはじき出されることになる。これが、光電効果であり、コンプトン散乱なので
ある。これらは、共に波長の短い(周波数の高い)時に起こる現象である。
このように、波長の短い(周波数の高い)時は、遠隔作用性が強まるのである。すでに
取り上げたウィーンの公式も、波長の短い(周波数の高い)時に非常によい近似を示すも
のである。光の粒子性とは、実は、電磁気作用の遠隔作用性だったのである。
これに対し、波長の長い(周波数の低い)時は、(疑似)近接作用性が強まる。このた
め、荷電粒子は波動的に振る舞う。したがって、黒体輻射の問題では『レイリー・ジーン
ズの公式』が成り立つことになるのである。つまり、レイリー・ジーンズの公式は、光の
波動性を示すというよりは、電磁気作用の疑似近接作用性を示すものだったのである。
以上のことをまとめていうならば、物質の世界では、遠隔作用と疑似近接作用とが混在
しているということである。波長が短く(周波数が高く)なれば遠隔作用性が強まり、波
長が長く(周波数が低く)なれば疑似近接作用性が強まる。プランクの公式も、実は、こ
のことを示しているのである。
ちなみに、プランクは、ウィーンの公式とレイリー・ジーンズの公式とを算術的に折衷
して、自身の公式を導いた。そして、その理論的根拠を後から考え出した。それが、『エ
ネルギー量子化仮説』であった。そして、その考えをさらに押し進めたのが、アインシュ
タインの『光量子仮説』であった。
だが、すでに見てきたように、そのような荒唐無稽な考え方は、もはや不要である。光
は波でも粒子でもないのだ。
振動数が低いときは波長も長いので、これらの荷電粒子は(疑似)近接作用的に振る舞う。
ところが、振動数が高いと波長が短くなる。そして、波長が荷電粒子間の距離の二倍未満
になってしまうと、もはや荷電粒子は(疑似)近接作用的に振る舞うことができなくなる。
このため、荷電粒子は遠隔作用的に振る舞うようになるのである。
これは、情報処理における『シャノンの標本化定理』と似ている。CDやMDのような
デジタル・オーディオでは、アナログ信号をデジタル信号に変換して記録されるわけだが、
標本化周波数の1/2を超える周波数の信号は、正しく変換できない。
これと同じように、上記の問題でも、周波数がある値よりも高いとき、すなわち、波長
がある値よりも短いとき、荷電粒子は(疑似)近接作用的に振る舞うことができず、遠隔
作用的に振る舞うことになるのである。
ちなみに、荷電粒子が(疑似)近接作用的に振る舞っている時は、作用によって受け取
った運動量や運動エネルギーが、各荷電粒子に分散される。ところが、遠隔作用的に振る
舞うときは分散されないので、作用を受けた粒子に運動量や運動エネルギーが集中するこ
とになる。このため、その荷電粒子だけが特別に大きな作用を受け、(場合によっては)
物質中からはじき出されることになる。これが、光電効果であり、コンプトン散乱なので
ある。これらは、共に波長の短い(周波数の高い)時に起こる現象である。
このように、波長の短い(周波数の高い)時は、遠隔作用性が強まるのである。すでに
取り上げたウィーンの公式も、波長の短い(周波数の高い)時に非常によい近似を示すも
のである。光の粒子性とは、実は、電磁気作用の遠隔作用性だったのである。
これに対し、波長の長い(周波数の低い)時は、(疑似)近接作用性が強まる。このた
め、荷電粒子は波動的に振る舞う。したがって、黒体輻射の問題では『レイリー・ジーン
ズの公式』が成り立つことになるのである。つまり、レイリー・ジーンズの公式は、光の
波動性を示すというよりは、電磁気作用の疑似近接作用性を示すものだったのである。
以上のことをまとめていうならば、物質の世界では、遠隔作用と疑似近接作用とが混在
しているということである。波長が短く(周波数が高く)なれば遠隔作用性が強まり、波
長が長く(周波数が低く)なれば疑似近接作用性が強まる。プランクの公式も、実は、こ
のことを示しているのである。
ちなみに、プランクは、ウィーンの公式とレイリー・ジーンズの公式とを算術的に折衷
して、自身の公式を導いた。そして、その理論的根拠を後から考え出した。それが、『エ
ネルギー量子化仮説』であった。そして、その考えをさらに押し進めたのが、アインシュ
タインの『光量子仮説』であった。
だが、すでに見てきたように、そのような荒唐無稽な考え方は、もはや不要である。光
は波でも粒子でもないのだ。