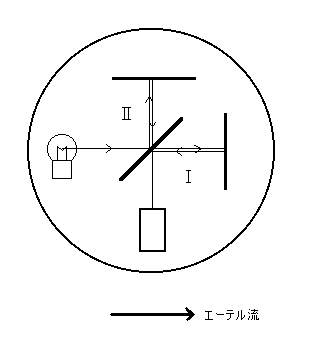
1.2 幾何光学の乱用
1.2.1 マイケルソン・モーレーの実験
アインシュタインがこの実験のことを知っていたかいなかったかはともかくとして、相対論のことを語る時、この実験のことを避けて通ることはできないだろう。
19世紀になると、『光は波である』という考え方が支配的になった。そこで、もし光が波であるとすると、それを伝えるための媒体が必要になってくる。そこで、光の波を伝える媒体とされたのが『エーテル』である。
地球はこのエーテルの海の中に浮かんでいると考えられていた。エーテルはまた、当時信じられていた『絶対空間』と同じ系に属するものと考えられていた。
さて、地球は太陽の中を公転している。ということは、エーテルの海の中を移動していることになる。これを地上の立場から見るならば、エーテルが地球に対して流れていることになる(エーテル流)。
一方、光を伝える媒体であるエーテルが流れれば、それに引きずられて、光の速度が変化するはずである。このエーテル流による光速度の変化を検出しようとしたのが、マイケルソン・モーレーの実験である。
光が同じ距離を往復するのでも、エーテル流に水平な方向に往復するのと、エーテル流に垂直な方向に往復するのとでは、エーテルの光速度への影響度が異なるため、所用時間が異なってくる。この所用時間の差を干渉縞の変化として検出するわけである。
それでは、所用時間は具体的にどれほどになるのか、以下に教科書にも載っている定説を述べてみよう。
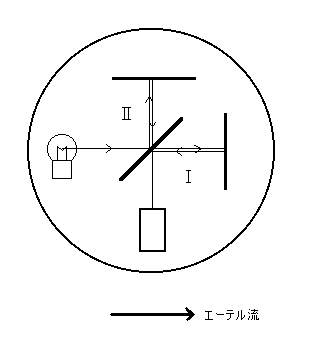
まず、エーテル流に水平な方向に往復する光の所用時間t1は、
t1 = L / ( c + v ) + L / ( c - v ) = 2Lc / ( c2 - v2 )
となる。
一方、エーテル流に垂直に往復する光の所用時間t2は、ピタゴラスの定理により、
L2 + { v( t2 / 2 ) }2 = { c( t2 / 2 ) }2
∴ t2 = 2L / { ( c2 - v2 )1/2 }
となる。
したがって、t1 - t2
を計算すれば、所用時間の差が求まることになる。
以上が教科書にも載っている定説である。